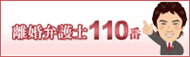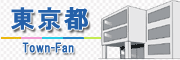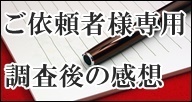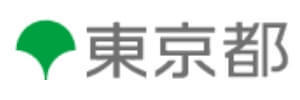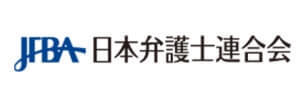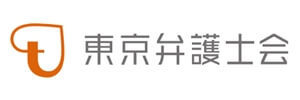東京都の探偵事務所 浮気調査・身辺調査・人探し・子供連れ去り・裁判資料
〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目14−4
ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア1008
東京メトロ日比谷線 銀座駅徒歩5分 東銀座駅徒歩1分
東京都公安委員会届出(第)30120216号
調査24時間対応
面談AM9:00~PM9:00
お役立ちリンク集
弁護士

依頼者に寄り添ったトータルサポートを提供している注目の専門家集団「ウカイ&パートナーズ法律事務所
若手士業によるトータルサポート体制──ウカイ&パートナーズ法律事務所の挑戦
渋谷に拠点を構える「ウカイ&パートナーズ法律事務所」は、法律・会計・登記の各分野に精通した若手士業が連携し、依頼者に寄り添ったトータルサポートを提供している注目の専門家集団。
士業の垣根を越えたワンストップサービス
同事務所の最大の特徴は、弁護士、公認会計士、司法書士といった異なる士業がパートナーシップを組み、連携して業務にあたる点にある。中小企業やベンチャー企業に対しては、会社設立の登記から税務申告、法的アドバイスまでを一貫してサポート。個人の依頼者に対しても、離婚、相続、不動産、破産といった複雑な問題に対し、各分野の専門知識を活かした包括的な対応が可能。
依頼者と同じ目線で、共に戦う
30〜40代の若手専門家が中心となって運営されている同事務所では、依頼者との距離感を大切にしている。堅苦しさを排し、相談しやすい雰囲気づくりを徹底。依頼者と同じ目線に立ち、共に課題に立ち向かう姿勢が、多くの信頼を集めている。
ベンチャー・中小企業を積極支援
渋谷という立地を活かし、スタートアップや中小企業の支援にも力を入れている。設立初期からの法務・会計・登記のトータルサポートにより、企業の成長を足元から支える体制が整っている。
明朗でリーズナブルな料金体系
料金面でも、依頼者にとっての「身近さ」を追求。日本弁護士連合会の旧報酬規定よりも安価な報酬体系を採用し、他士業との連携による業務でも提携価格が適用されるなど、コストパフォーマンスの高さも魅力。

「安心・信頼・納得」を届ける法律のパートナーすずたか総合法律事務所
弁護士・鈴木隆弘氏によって設立された「すずたか総合法律事務所」は、20年以上にわたり、個人・法人を問わず幅広い依頼に応えてきた実績を持つ法律事務所。依頼者の心に寄り添いながら、迅速かつ丁寧なリーガルサービスを提供する姿勢が、多くの信頼を集めている。
法律のプロフェッショナルが連携する安心の体制
同事務所では、弁護士と事務職員が密に連携し、依頼者の多様な法的ニーズに対応。企業法務から個人のトラブルまで、豊富なノウハウを活かして一つひとつの案件に丁寧に向き合っている。特に、依頼者の利益を最優先に考える姿勢は、事務所の根幹をなす価値観。
迅速かつ丁寧な対応で、信頼を築く
「レスポンスの速さは誰にも負けない」という言葉どおり、スピード感のある対応と、わかりやすく親切な説明を両立。単なる迅速さではなく、質の高い仕事にこだわる姿勢が、依頼者の安心感につながっている。
経営理念に込められた想い
すずたか総合法律事務所の経営理念は、「For your peace life.」──安心、信頼、納得が人の幸せにつながるという信念のもと、法的サービスを通じて依頼者の心にあたたかい光を灯すことを使命としている。
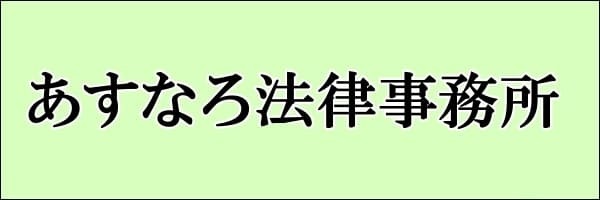
成長と信頼を象徴する法律事務所─あすなろ法律事務所
依頼者の悩みに真摯に向き合い、迅速かつ的確な対応で信頼を築く──そんな理念を掲げて活動するのが「あすなろ法律事務所」だ。所長を務める國田武二郎弁護士は、検察官としての豊富な経験と、教育・社会貢献活動を通じた幅広い知見を活かし、日々法的支援に取り組んでいる。
検察官としての実績を礎に、依頼者に寄り添う弁護士へ
國田弁護士は、東京・名古屋・横浜など全国の地方検察庁で、財政・経済事件から少年事件まで多岐にわたる案件を担当。仙台高等検察庁では若手検事の育成にも尽力した。平成15年に弁護士登録後は、刑事弁護を中心に活動を展開し、依頼者の立場に立った丁寧な対応を信条としている。
「依頼者の気持ちに立ち、悩みを一日でも早く解消したい」その思いを胸に、國田氏は日々研鑽を重ね、迅速かつ果敢な代理人としての役割を果たしている。
教育・社会貢献にも積極的に取り組む
現在は愛知学院大学法科大学院の教授として、刑事訴訟法や法曹倫理を教えるほか、産業保健総合支援センターの相談員として、企業のメンタルヘルスに関する法的課題にも対応。また、厚生労働省の委嘱により、年金記録訂正審議会の委員としても活動している。
さらに、出身地・石川県志賀町では定期的に無料法律相談を実施。メディア出演やドラマの検察監修など、法の専門家としての知見を広く社会に還元している。
「あすなろ」に込めた成長と志
事務所名の「あすなろ」は、國田氏の故郷・石川県能登地方に自生する木に由来する。「明日はヒノキになろう」という意味を込めたこの名には、常に成長を目指す姿勢と、依頼者と共に歩む決意が込められている。
主な著作・活動実績
- 『日本法の論点〈第1巻〉』~取調べの可視化に対する現状とその対応~
- 『現代刑法各論』~判例重視・実務感覚が身につく司法試験受験用教科書~
- NHKドラマ『鉄の骨』検察考証担当
- CBCラジオ「朝からPON」法律コーナー出演
法律相談

法的トラブルの“道しるべ”─全国どこでも頼れる「法テラス」
借金、離婚、相続、そして犯罪被害──人生の中で突然直面する法的トラブル。そんなとき、「誰に相談すればいいのか分からない」「どんな制度があるのか知らない」と戸惑う人も少なくない。そんな不安を抱える人々の“最初の相談窓口”として、全国で頼りにされているのが「法テラス(日本司法支援センター)」。
国が設立した法的支援の総合案内所
同法テラスは、法的トラブルの解決に必要な情報やサービスを、誰もがどこでも受けられるようにと国によって設立された公的機関。全国各地に地方事務所を展開し、地域に根ざした法的支援を提供している。
無料で受けられる情報提供と相談案内
法テラス・サポートダイヤルや各地の窓口では、トラブルの内容に応じて適切な相談先や、関連する法制度の情報を無料で案内。たとえば「離婚したいがどう進めればいいか分からない」「借金問題を誰に相談すればいいか分からない」といった悩みに対し、解決への“道案内”をしてくれる。
経済的に困難な方への法的支援も充実
経済的な事情で弁護士や司法書士への相談をためらっている人に対しては、無料の法律相談や、事件解決にかかる費用の立替制度も用意。安心して専門家に依頼できる環境が整っている。
犯罪被害者や法的過疎地への支援も
法テラスでは、犯罪被害にあった方への支援にも力を入れており、被害者支援に理解のある弁護士の紹介も行っている。また、弁護士などの専門家が身近にいない地域には、法テラス所属の弁護士が常駐する「地域事務所」を設置。地域格差のない法的サービスの提供を目指している。
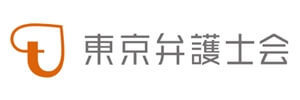
日本最大規模の弁護士会──東京弁護士会が目指す「身近な法律のパートナー」
「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」を使命に掲げ、市民にとって身近な存在であり続けることを目指す─それが、東京弁護士会の姿勢。約9,300人の弁護士が所属するこの団体は、日本最大規模を誇る弁護士会として、幅広い法的課題に取り組んでいる。
歴史と伝統に裏打ちされた信頼
東京弁護士会のルーツは、1880年に設立された「東京代言人組合」にさかのぼる。1893年、弁護士法の公布に伴い「東京弁護士会」として正式に発足。以来140年以上にわたり、日本の法曹界を牽引してきた。
多様な人権課題に取り組む専門集団
東京弁護士会は、刑事弁護をはじめ、子ども、高齢者、障がい者、女性、外国人、消費者、犯罪被害者、公害・環境といった幅広い分野の人権問題に対応。社会の変化に応じて、法的支援のあり方を柔軟に進化させている。
市民に開かれた法律相談サービス
「法律は難しい」「弁護士は敷居が高い」と感じる市民にも安心して利用してもらえるよう、東京弁護士会では法律相談サービスの拡充に注力。誰もが気軽に法的アドバイスを受けられる環境づくりを進めている。
社会への提言と制度改革への働きかけ
人権擁護の立場から、司法制度の適正化や立法政策の改善に向けて、声明や意見書を積極的に発表。法務省や裁判所との協議も行い、制度の改善に向けた働きかけを続けている。また、自治組織として、弁護士自身の改革にも取り組み、より信頼される法曹界の実現を目指している。

首都・東京を支える法律専門家の集団─第一東京弁護士会
世界有数の大都市・東京。その中心で、法の専門家として多様な分野に貢献しているのが「第一東京弁護士会」。東京都内に事務所を構える弁護士によって構成されるこの団体は、行政、司法、企業、地域社会と幅広く連携し、法的支援の最前線を担っている。
首都・東京というフィールド
東京都は、人口約1,300万人、周辺県を含めると約3,500万人が暮らす巨大都市。商業、工業、金融、エンターテインメントなど多様な産業が集積し、数多くの企業が本社を構えるビジネスの中心地でもある。また、国の官庁や公益法人、各種団体の本部も集中し、法的ニーズは極めて多岐にわたる。
このような都市環境の中で、第一東京弁護士会は、地域と社会の法的インフラを支える重要な役割を果たしている。
裁判所との密接な関係と多様な活動領域
東京には、最高裁判所をはじめ、東京高等裁判所、知的財産高等裁判所、東京地方裁判所、東京家庭裁判所(および立川支部)、さらに9つの簡易裁判所が設置されている。第一東京弁護士会の会員は、これらの裁判所と連携しながら、調停委員、成年後見人、破産管財人、国選弁護人などとしても活躍している。
また、都庁や市区町村、国家官庁、各種法人・団体からの推薦依頼にも応じ、行政委員会の委員や各種公職への推薦も行っている。
弁護士の専門性を社会に還元
第一東京弁護士会の弁護士たちは、司法の現場だけでなく、行政や公益活動の分野でもその専門性を発揮。社会の多様な課題に対し、法の力で解決策を提示する存在として、信頼を集めている。
なお、東京には第一東京弁護士会のほかに、第二東京弁護士会、東京弁護士会の計3つの弁護士会が存在する。いずれの会に所属していても、日本の弁護士資格を持つ者は全国どこでも活動が可能。

自由な気風と市民目線で時代を切り拓く─第二東京弁護士会
東京にある3つの弁護士会の中で最も若く、自由闊達な気風を誇るのが「第二東京弁護士会(通称:二弁)」だ。新しい社会の動きを積極的に取り入れ、多様な分野で意欲的に活動を展開している。
三会の一翼を担う、東京の弁護士会
東京には、東京弁護士会、第一東京弁護士会、そして第二東京弁護士会の3つの弁護士会が存在し、いずれも日本弁護士連合会(日弁連)に所属している。三会にはそれぞれ独自の気風があるが、上下関係や地域割りはなく、相互に協力しながら市民の法的ニーズに応えている。
その中で、第二東京弁護士会は「市民に最も身近な法律家集団」として、柔軟で開かれた姿勢を大切にしている。
市民の権利を守る多彩な取り組み
二弁は、市民の権利実現に向けた活動に特に力を入れており、以下のような制度や支援を展開している:
- 法律相談センターの設置による身近な法的アドバイスの提供
- 手頃な費用で迅速な解決を目指す仲裁センターの運営
- 逮捕された人のもとに弁護士が駆けつける「当番弁護士制度」
- 民事介入暴力、セクシュアル・ハラスメント、消費者問題、外国人の人権問題などへの迅速な対応
これらの取り組みは、法の専門家としての責務を果たすと同時に、市民の安心と信頼を支える基盤となっている。
国際化と専門性の強化にも注力
第二東京弁護士会は、会員弁護士の資質向上にも積極的だ。研究会や研修の実施に加え、留学制度や海外弁護士会との交流、国際業務に対応するための海外連携弁護士紹介制度など、グローバルな視野を持った法的支援体制を整えている。
また、弁護士自治の理念のもと、会員の規律を保ち、信頼される法曹集団としての自律性も大切にしている。
「時代と社会を見つめる」弁護士会として
第二東京弁護士会は、日々の活動を通じて社会の変化を敏感に捉え、市民の声に耳を傾けながら、法の力でより良い社会の実現を目指している。自由な発想と実行力を兼ね備えたこの弁護士会は、これからの時代にふさわしい法の担い手として、ますます注目を集めていくだろう。
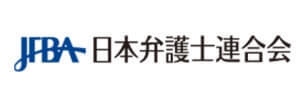
法の力で社会を支える─多角的な取り組み日本弁護士連合会
日本全国の弁護士を統括する「日本弁護士連合会(日弁連)」は、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命を果たすため、幅広い分野で積極的な活動を展開している。単なる職能団体にとどまらず、社会課題に法的視点から向き合う“公共的存在”として、司法制度の発展と市民の権利保護に貢献している。
行動の指針:「人権のための行動宣言」と「会務執行方針」
日弁連は、活動の根幹として「人権のための行動宣言」を策定し、毎年度「会務執行方針」を定めている。これらを基盤に、弁護士が日常業務を超えて社会課題に取り組むための方向性を明確にし、実効性ある活動を推進している。
主な活動分野
- 人権擁護活動 | 各種委員会を通じて人権侵害の救済や課題解決に取り組む。
- 刑事司法の改革 | 違法な取調べや冤罪を防ぐため、制度改善に向けた調査・提言を実施。
- 民事司法の改革| 市民にとって利用しやすい司法制度の整備を目指す。
- 司法基盤の整備| 市民のための司法を実現するため、制度全体のインフラを拡充。
- 次世代法律家の育成| 法科大学院生や司法修習生への支援を通じて、未来の法曹を育てる。
- 弁護士業務の改革 | 社会の変化に対応し、弁護士の職務や倫理の在り方を見直す。
- 法的サービスの拡充 | 行政や団体と連携し、法的支援をより身近なものに。
- 国際活動| 国際人権問題への対応、国際交流、弁護士の国際業務支援などを展開。
社会とともに歩む、法の担い手として
日弁連の活動は、単なる制度運営にとどまらず、社会の変化や市民の声に応える柔軟で実践的な取り組みに満ちている。国内外の課題に対して法的な視点からアプローチし、より公正で持続可能な社会の実現を目指す姿勢は、まさに“司法の中枢”としての責任と覚悟の表れ。
公的機関

安心・安全な消費生活を支える司令塔──消費者庁の多角的な取り組み
私たちの暮らしに密接に関わる「消費」。その安全性や公正性を守るため、国の中枢で消費者政策を統括しているのが「消費者庁」だ。消費者庁は、日々変化する社会環境や取引形態に対応しながら、消費者の権利と利益を守るために幅広い施策を展開している。
消費者政策の企画と推進
政府全体の消費者政策を一体的に進めるため、「消費者政策基本計画」を策定し、毎年その進捗を検証・評価。
高齢化やデジタル化の進展を踏まえ、消費者法制度の抜本的な見直し(パラダイムシフト)にも着手。
消費者被害の防止と救済
インターネット取引や悪質商法による被害の拡大を防ぐため、特定商取引法や景品表示法を厳正に執行。
消費税の転嫁拒否や不当表示の是正など、事業者の適正な表示を促進。
消費者安全調査委員会を通じて重大事故の原因を究明し、再発防止策を提言。
持続可能な社会に向けた取り組み
SDGs(持続可能な開発目標)の推進や、消費者志向経営(サステナブル経営)の支援を通じて、持続可能な社会づくりに貢献。
消費者教育と制度整備
「消費者教育推進法」に基づき、消費者教育推進会議を活用して、消費者市民社会の実現を目指す。
公益通報者保護制度の普及や、消費者契約ルールの整備など、制度面からも消費者を支える。

暮らしの安全を守る情報のハブ─警視庁の多角的な取り組み
東京都民の安全と安心を守る中核機関として、日々多岐にわたる業務を担っている警視庁。その公式情報は、利用者が目的に応じてスムーズにアクセスできるよう、大きく6つのカテゴリに分類されている。市民の暮らしに密着した情報から、緊急時の対応まで、幅広い内容が網羅されているのが特徴。
安全な暮らし
「安全・安心なまちづくり」をテーマに、特殊詐欺の注意喚起や災害への備え、情報セキュリティ対策など、日常生活に潜むリスクから身を守るための情報を提供。犯罪や災害に巻き込まれないための予防策が、わかりやすくまとめられている。
交通安全
交通事故の防止や道路環境への配慮、交通規制の情報など、都内の交通に関するあらゆる情報を網羅。標識や信号機に関する意見募集や、ゲーム感覚で交通ルールを学べるコンテンツも用意されており、子どもから大人まで幅広い層に向けた啓発が行われている。
相談・お悩み
少年相談や犯罪被害者支援、落とし物の届け出など、市民の不安や困りごとに寄り添う窓口情報を集約。身近な悩みに対応するための相談体制が整備されており、誰でも安心してアクセスできる仕組みが構築されている。
手続き
交通関連の申請をはじめ、風俗営業、銃砲所持、警備業、古物営業、探偵業、渡航証明など、さまざまな許認可手続きに関する情報を提供。必要な書類や手続きの流れが明確に示されており、スムーズな申請をサポートしている。
事件・事故
110番通報の適切な利用方法や、事件・事故の発生情報、身元不明者の情報、公開捜査の内容など、緊急性の高い情報をタイムリーに発信。市民の協力を得ながら、事件解決や安全確保に努めている。

国民の権利と社会の秩序を守る─裁判所の仕事とは?
私たちの暮らしの中で、法律に関わるトラブルや事件が起きたとき、最終的な判断を下すのが「裁判所」だ。個人間の紛争から刑事事件、家庭内の問題まで、裁判所は多岐にわたる法的課題に対応し、国民の権利を守り、社会の平穏と安全を支えている。
裁判所の基本的な役割
裁判所の主な仕事は、以下の2つに集約される
- 民事や家事などの法律的な紛争を解決すること
- 犯罪を犯したとされる人が有罪か無罪かを判断すること
これらを通じて、国民の権利を守り、法の下の公平を実現している。
裁判所が扱う主な事件の種類
- 民事事件| 金銭トラブルや契約違反など、個人や企業間の紛争を解決する。労働問題、知的財産権、破産、保護命令なども含まれる。
- 行政事件| 国や自治体の行政処分に対する不服申し立てなど、行政との争いを扱う。
- 刑事事件| 窃盗や詐欺などの犯罪について、被告人が有罪か無罪かを判断する。
- 家事事件| 離婚、相続、親権など、家庭内の法的問題を解決する。
- 少年事件| 非行に及んだ少年に対し、再非行防止のための適切な措置を決定する。
- 医療観察事件| 心神喪失状態で重大な犯罪を行った人に対し、医療的処遇の必要性を判断する。
裁判以外の解決手段も
民事紛争の中には、裁判所を通じた「判決」や「和解」「調停」だけでなく、ADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる方法で解決されるケースもある。これにより、より柔軟で迅速な解決が図られることもある。

消費者の声を社会に届ける中核機関─国民生活センターの使命と行動指針
消費者の安全と安心を守るために、日々最前線で活動を続ける「国民生活センター」。この機関は、消費者問題や暮らしの課題に対して、調査・分析・情報提供・政策提言などを通じて多角的に取り組む、わが国の消費者行政の中核的存在だ。
平成27年4月、独立行政法人制度の見直しに伴い、中期目標管理型の独立行政法人として新たなスタートを切った同センターは、組織としての「使命」と、役職員一人ひとりの「行動指針」を明文化。この理念のもと、より信頼される機関としての進化を続けている。
国民生活センターの使命:信頼でつなぐ、暮らしと社会
国民生活センターの使命は、消費者・生活者、事業者、行政を「たしかな情報」でつなぎ、公正で健全な社会と、安全・安心な生活の実現を目指すことにある。
この「たしかな情報」とは、単なるデータや知識ではなく、現場で得られたリアルな声や、科学的根拠に基づいた検証結果、そして社会的に中立な立場から導き出された知見を指す。センターは、こうした情報をもとに、消費者被害の未然防止や制度改善に貢献している。
行動指針:5つの実践原則で支える現場力
国民生活センターの役職員は、以下の5つの行動指針を日々の業務の中核に据えている。
- 現場の強みと消費者の声を活かす
消費生活相談や商品テスト、事故情報の収集など、現場で得られる一次情報を重視。寄せられる声を単なる苦情として処理するのではなく、社会全体の課題として捉え、政策提言や注意喚起に活かしている。 - 消費者・生活者の目線を大切にする
消費者問題は、誰にでも起こりうる身近なリスク。センターでは、専門家の視点だけでなく、当事者の立場に立った「生活者目線」で問題を深掘りし、より実効性のある対応策を導き出している。 - 個人の主体性と組織の一体性を発揮する
役職員一人ひとりが自ら考え、行動する主体性を持ちながら、チームとしての連携も重視。組織全体で創意工夫を重ね、柔軟かつ迅速な対応を可能にしている。 - すばやく・的確に・分かりやすく
収集した情報は、スピード感を持って整理・分析し、誰にでも理解できる形で発信。消費者・事業者・行政のすべてにとって有益な「信頼できる情報源」としての役割を果たしている。 - 専門組織としての知見と精神を引き継ぐ
- 長年にわたり培ってきた専門性と公共性を継承しつつ、時代の変化に応じて知見をアップデート。消費者問題の専門機関として、常に進化し続ける姿勢を貫いている。
社会の変化に応える柔軟な姿勢
近年では、デジタル化や高齢化、国際化といった社会の変化に伴い、消費者問題も複雑化・多様化している。国民生活センターは、こうした新たな課題にも柔軟に対応し、消費者教育の推進や地方自治体との連携、企業への注意喚起など、多方面にわたる活動を展開している。
東京探偵事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4丁目14−4 ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア1008
アクセス
東京メトロ 銀座駅徒歩5分
東銀座駅徒歩1分
営業時間
| 相談 | 24時間 |
|---|---|
| 調査 | 24時間 |
| 面談 | 9:00~21:00 |
弁護士の先生へ
東京探偵事務所は調査技術、撮影技術には絶対の自信があり、これまでも2万以上に及ぶ裁判資料の為の調査を承っています。
調査報告書については、相手側より「指摘されない報告書」を作成する事を心がけております。
調査が必要な場合が御座いましたら、お客様に負担が少なくなるよう低料金にて対応いたします。
ご検討をお願い致します。